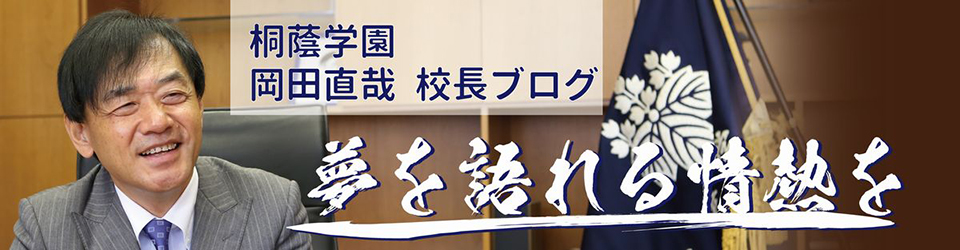昨日(12/20)、中学女子部1年で、カレーランチ会を実施しました。
その月に誕生日を迎える1年生とともに、昼休みにカレーライスをいただく企画です。12月生まれの5名が校長室にやってきました。
各自でライスをよそって(今日は皆控えめですね…)、
私(岡田)が一人ひとりにルーをかけていきます。
最初はちょっぴり緊張気味の5人でしたが、徐々にリラックスしてきました。個性的な5人で話題が豊富、会話が弾みます。中学入学後に囲碁を始め、なんと全国大会に出場した(!)生徒もいました(本人は照れていましたが…)。
ほとんどの生徒がお代わりをし(最初の「盛り」は控えめでしたが…)、最後はルーの鍋が空っぽになりました。
さらに、女子部統括部長の平岡先生からケーキの差し入れが! あれだけカレーを食べてもケーキはやはり「別腹」のようです。
今月も大変楽しい会となりました。生徒たちはこの企画を楽しみにしてくれているようですが、私にとっても、生徒たちと直接話ができる大切なイベントの一つとなっています。