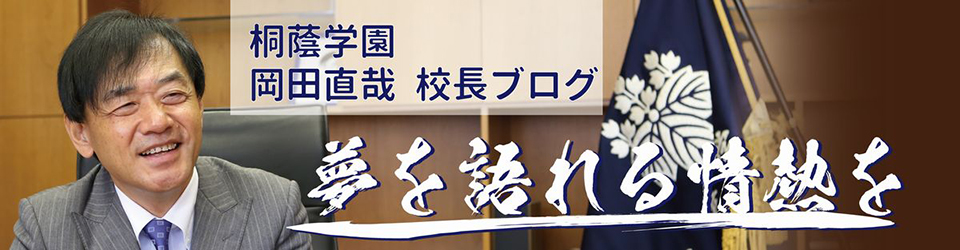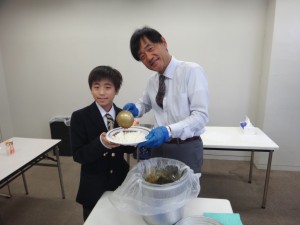12/15(土)、中等教育学校の入試体験会・入試説明会が行われました。あと1か月半後に迫った中等教育学校の入学試験。その本番さながらの体験をすることができるチャンスです。499名の小学校6年生がチャレンジしてくれました。
私(岡田)は各受験教室を回り、受験生たちを激励しました。
「みなさん、緊張していますか? 本番はもっと緊張することでしょう。しかし、緊張するのは良いことです。なぜなら、緊張するのはしっかりと準備をしてきた証拠だからです。本番で緊張したら、このことを思い出してください。」
「いよいよ4月から男女共学となる新しい中等教育学校がスタートします。皆さんがその新しい歴史を創る主人公になってくれたら本当に嬉しく思います。」
皆さん真剣に聞いてくれました。
一方、シンフォニーホールでは入試説明会が同時進行。こちらにも多くの皆さまにご来場いただきました。
まずは私からご挨拶。
「桐蔭学園は、変化の激しい次の時代においても力強く生きていける人物を育てるべく、アクティブラーニング型授業、探究、キャリア教育を三本柱に据えた『新しい進学校』を目指しています。」
「私は、お子様が中学入試を通じて大きく成長することを願っています。そのために大切なことは、お子様が自己肯定感を得ることです。ぜひ、お子様をほめてあげてください。」
終了後、帰途に就く皆さまをお見送りしました。
「どうだった? よく頑張ったね!」とお子様にお声かけされている保護者の方を多くお見受けしました。そうです。これがお子様の成長につながるのです。見ているこちらが嬉しくなりました。
これをもちまして、来年2月の入試に向けた説明会・体験会はほぼ終了いたしました。
3月の「スタートアップ! 学校説明会」にはじまり、オープンスクール、夏/秋の説明会、そしてこの日の入試体験会・入試説明会と、本当に多くの皆さまがお運びくださいました。毎回大きな反響をいただき、教職員一同、励みになると同時に責任の大きさを痛感することとなりました。あらためて御礼申し上げます。
4月には男女共学となる新しい中等教育学校がスタートします。桐蔭学園の新しい歴史の始まりです。満開の桜の下、皆さまとお会いできることを楽しみにしております。