
桐蔭横浜大学の共通教育プログラム「MAST」に新設した 「アスリート・イン・ソサエティ」は、アスリート学生やスポーツに関心のある学生が、社会とスポーツのあり方を深く考えることを通じて、人間として、社会人として大きく成長すること(「文部両道」)を狙いとした科目群であり、部活動に所属する学生に広く履修を推奨しているものです。
アスリート・イン・ソサエティ科目群の一つを、岡部 智洋客員教授(日本テレビホールディングス㈱執行役員、㈱ティップネス代表取締役社長)がコーディネートする「学長特別授業」として開講します。
特別講師の知見と経験に基づく授業内容から、リアルなスポーツビジネスの世界を知ることができます。部活動で競技力の向上やチームワークを学ぶとともに、特別授業で知識を蓄え、人間力を高める。 アスリートとしても、人間的にも、そして社会人としても大きく育って欲しい、まさに「文部両道」の実現を目指しています。
アスリート・イン・ソサエティ
共通教育プログラム「MAST」に新設された「アスリート・イン・ソサエティ」は、社会とスポーツのあり方について、深く考えます。 これにより、ユニバーシティ・ポリシーに定める6つの力「TOIN6」を身に着け、 人間として、社会人として大きく成長すること(「文部両道」)を狙いとした科目群です。

ビッグゲストを招く学長特別授業
2024年度の第1学期、アスリート・イン・ソサエティ科目群の一つを、岡部 智洋客員教授(日本テレビホールディングス㈱執行役員、㈱ティップネス代表取締役社長)がコーディネートする「学長特別授業」として開講しています。メディアやスポーツビジネスの最前線で活躍する特別講師陣を招いた授業です。
第1回(2024/4/18) 岡部 智洋客員教授(日本テレビホールディングス(株)執行役員、(株)ティップネス社長)
第2回(2024/4/25)株式会社WOWOW 代表取締役・会長執行役員 田中 晃氏
第3回(2024/5/ 9) 株式会社アールビーズ 代表取締役社長 黒崎 悠氏
第4回(2024/5/16) 一般社団法人渋谷未来デザイン General Producer 金山 淳吾氏
第5回(2024/5/23)株式会社 読売新聞東京本社 アライアンス戦略本部次長 黒川 岩人氏
第6回(2024/5/30)公益財団法人 日本バドミントン協会 代表理事 村井 満氏
第7回(2024/6/6) 日本テレビ コンテンツ戦略局アナウンス部 田中 毅氏・郡司 恭子氏
第8回(2024/6/13)ぴあ株式会社 スポーツ・ソリューション推進局 上席執行役員 永島 誠氏
第9回(2024/6/20)株式会社GWC 代表取締役(アースフレンズ東京Z代表) 山野 勝行氏
第10回(2024/6/27)プーマジャパン株式会社 マーチャンダイジング本部 合志 卓也氏
第11回(2024/7/4) 株式会社トリデンテ 代表取締役 佐々木 惇氏
第1回(2024/4/18)

岡部 智洋客員教授
日本テレビホールディングス(株)執行役員、
(株)ティップネス社長
初回の授業は、「アスリート・クロス」の講義の目的を、「日本のスポーツビジネスの成長に貢献できる人材の育成」とした上で、先ずは、マクロの視点で、現在の日本が抱える社会課題の現状と解決策を考える回となりました。 「超高齢化社会における社会保障費負担の増大」、「働き世代のメンタルヘルスケア」等は、スポーツ参加率の向上で多少の解決が出来ると言われていますが、その参加率はスポーツ庁が掲げる目標値の70%には届きません。参加率向上に向けて、何を行っていけば良いのかを学生と一緒に議論しました。 また、「生活者のスポーツの接点機会創出」の具体的事例として、フィットネス事業「ティップネス」が行っている産学連携企画や、日本テレビの「カラダWEEK」など様々な施策を紹介しました。
第2回(2024/4/25)
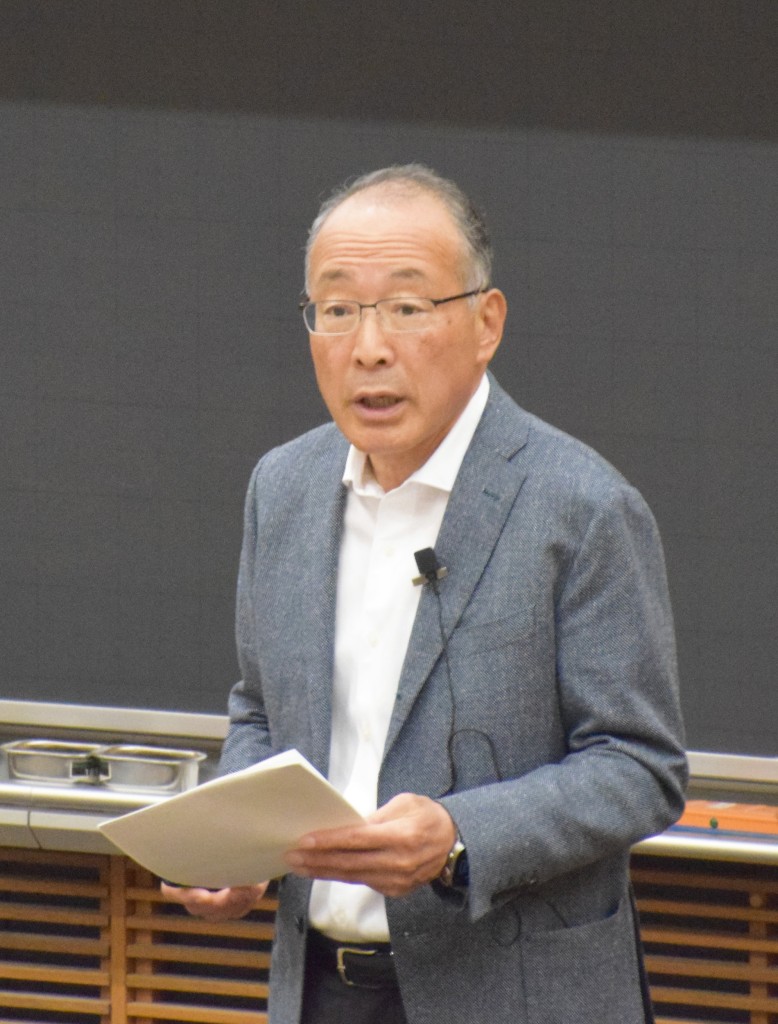
田中 晃氏
株式会社WOWOW 代表取締役 会長執行役員
「PHILOSOPHY For SPORTS」というテーマを、「WHY(なぜ)」という切り口で学生と一緒に考える授業となりました。 「スポーツとメディアの関係」から始まり、「箱根駅伝が見る人を魅了するのは何故か?」、「Jリーグの本質的な価値とは何か?」、「パラスポーツに社会を変える力はあるか?」など、WOWOWでの取り組みや、田中氏が会長を務める「日本車いすバスケット連盟」での具体的事例を交え、ご紹介いただきました。 ご自身の「スポーツへの哲学」と「スポーツへの溢れる熱意」が溢れる授業となり、大学スポーツの成長に向け、常に疑問を持って学生自身が考えることの大切さを深く考えさせられる授業となりました。
第3回(2024/5/9)

黒崎 悠氏
株式会社アールビーズ代表取締役社長
黒崎氏自身の「箱根駅伝出場」などの陸上競技の経験から、現在のランニング関連ビジネスに繋がった「スポーツビジネスとの出会い」という貴重なお話をいただきました。 その上で、「ランニングと健康効果」、日本における「ランニング関連ビジネス事情」や、特に日本での「マラソン事業の社会的意義」について深く学びました。地域におけるマラソン大会の開催は、「地域経済の活性化」や、「住民の健康意識向上」、そして経済効果も大きく、日本のマラソンのパフォーマンス向上にも繋がっています。 学生と「20代が参加したくなるマラソン大会」について考え、議論を行いました。
第4回(2024/5/16)

金山 淳吾氏
一般財団法人 渋谷観光協会 代表理事
金山氏、ダブルダッチ世界選手権3連覇のKEITA JUMPROCK氏、渋谷未来デザインなどでプロデューサーとして活躍する秋葉直之氏の3人で授業が進められました。KEITAさんと学生でダブルダッチのアイスブレークから始まり、「スポーツをつくる」というテーマに向け、アーバンスポーツを中心に事例が紹介されました。個性とクリエイティビティ豊かな3人の講師に引っ張られ、学生からも「+-×÷を使って新しいスポーツを考える」という課題に対して、面白い発想や企画が続出しました。渋谷を中心とした「街から発信されるスポーツの在り方」や「ストリートスポーツの魅力」に触れ、横浜市青葉区から発信されるスポーツについて考えました。
第5回(2024/5/23)

黒川 岩人氏
株式会社 読売新聞東京本社 アライアンス戦略本部次長
読売新聞社で17年間、野球事業に携わってきた黒川氏から、野球の興行において大事にしていることや、日本のプロ野球の歴史についてなど、多岐にわたるお話をいただきました。90年前、大リーグ選抜チーム招聘の際に、選抜チームと大日本東京野球倶楽部(現在の読売巨人軍)が対戦して以降、日米野球は継続して開催され、2006年にWBCが誕生し、2019年のイチロー選手の引退試合となったMLB開幕戦の日本開催にも繋がっている話は、改めて、スポーツ事業の「継続性」と「意志」の大事さを痛感しました。また、興行において大事なのは、観戦者・関係者の「安全確保」や「体験価値の向上」、そして「マネタイズ」という話があり、「社会貢献できてこそ良い商売」という黒川氏の言葉も、スポーツビジネスの本質を考える機会となりました。
第6回(2024/5/30)
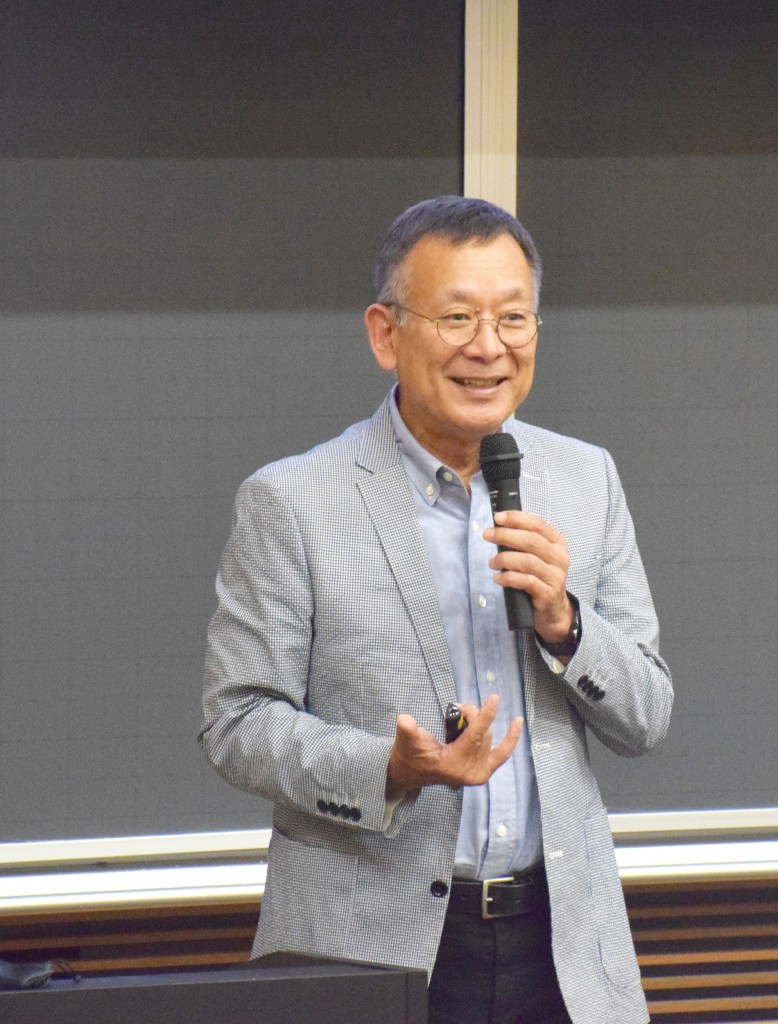
村井 満氏
公益財団法人 日本バドミントン協会 代表理事
リクルートエージェント社長などを経て、Jリーグ第5代チェアマンとして財政再建を始め改革路線を推し進めた村井氏。激動のJリーグの立て直しに向け、「世の中で誰もやっていない事をやってきた」と自負する村井氏から、数々の名言が繰り広げられた講義となりました。「再現性からの超越」、「始動性(ファーストペンギン)」、「傾聴力と主張力」、「計画された偶発性」など、学生の皆さんにとっても、スポーツビジネスの学びにとどまらず、競技力の向上にも繋がる教えの数々に、積極的な質疑応答も行われました。数々のイノベーションを起こしてきた村井氏ならではの「変革には足を使う」という言葉と、それにまつわるエピソードの数々は、「toin6」の考えの一つである「探求力」を養う良質な講義になりました。
第7回(2024/6/6)

田中 毅氏・郡司 恭子氏
日本テレビ コンテンツ戦略局アナウンス部
「スポーツ実況の裏側」と題して、日本テレビのスポーツ中継、ニュース・情報番組で活躍する田中さんと郡司さんの両アナウンサーを招いての特別講義となりました。 講義前半は「発声練習」や「早口言葉」の実演で教室全体が盛り上がり、後半は「立体的に伝える」という視点での座学などで、現役アナウンサーならではの「プロフェッショナル」な仕事ぶりをリアルに実感できる機会となりました。テレビ事業が公共の電波での免許事業だからこそ、「文化の醸成」への貢献も担っており、伝える際に大事な事は「客観と主観」のバランスというのも、学生の皆さんにとっては興味深い内容になったようです。講義全体を通して学んだ「本番に向けての徹底的な準備」と「価値を伝える技術」の二点は、競技力を高める上でも、社会人への準備に向けても、学生が考動する上で大事な要素なので有意義な授業となりました。
第8回(2024/6/13)

永島 誠氏
ぴあ株式会社 スポーツ・ソリューション推進局 上席執行役員
この回では、エンタメメディアのハシリとも言える「ぴあ株式会社」の執行役員を務める永島さんから、「ぴあ」の理念とも言える「感動のライフラインの実現」に向けた様々な施策の解説を頂きました。特にスポーツやエンターテインメントでの集客最大化に向けて大事な要素とは何かを、具体的事例を交えてご教示頂き、学生スポーツの在り方についても多くを学べる機会となりました。今回の講義のテーマは「アスリートを支える視点で、パートナー(協賛社)は何が出来るのか?」でしたが、「スポーツマーケティングの本質」ともいえるテーマだけに、学生たちの現在、そして未来においてもそれぞれの立場でしっかり考える事が出来た授業になりました。
第9回(2024/6/20)

山野 勝行氏
株式会社GWC 代表取締役(アースフレンズ東京Z代表)
Bリーグチームで唯一の個人オーナーとも言える山野さんの描く「逆転ストーリー」は、とても興味深いものでした。華やかな表舞台からは想像しづらい、地道ながらも全てにおいて共通する「分岐点は人間力」という山野さんの言葉は学生の皆さんに考えさせられるものでした。なぜベンチャー企業でプロバスケットボール事業を始めたのか?その理由や、その上で必要なこと、10年間にわたり地域活動などで行ってきたことを、山野さんの尽きることない情熱を交え、余すことなくお話頂きました。「苦しい時ほど頑張る、挑戦する」という山野さんの姿勢に刺激を頂いた学生の方も多かったと思います。「ホームタウンの皆さまにワクワクして欲しい」という山野さんの想いは、学生スポーツにとっても大事な事として学ぶ機会となりました。
第10回(2024/6/27)

合志 卓也氏
プーマジャパン株式会社 マーチャンダイジング本部
本学の卒業生であり、スポーツビジネスの最前線で働く合志さんの話は、学生により身近なものとして伝わったことでしょう。先のサッカーワールドカップにおける「三笘の1ミリ」を演出した「PUMA」のスパイクは、彼のサポートがあって三笘選手が着用していたことも驚きでしたが、それに関わっている方が本学の卒業生ということがとても嬉しく思えました。「マーケティング」「マーチャンダイジング」という言葉の本質についても詳しく触れていただき、関連したスポーツメーカーと選手の契約に関する話や、商品の企画・開発に携わる現場での苦労話ややりがいなどについても、面白おかしくお話しいただきました。 「桐蔭横浜の卒業生として自信を持ってください!」という合志氏の言葉に、希望を見出した学生も多くいたのではないかと思います。
第11回(2024/7/4)
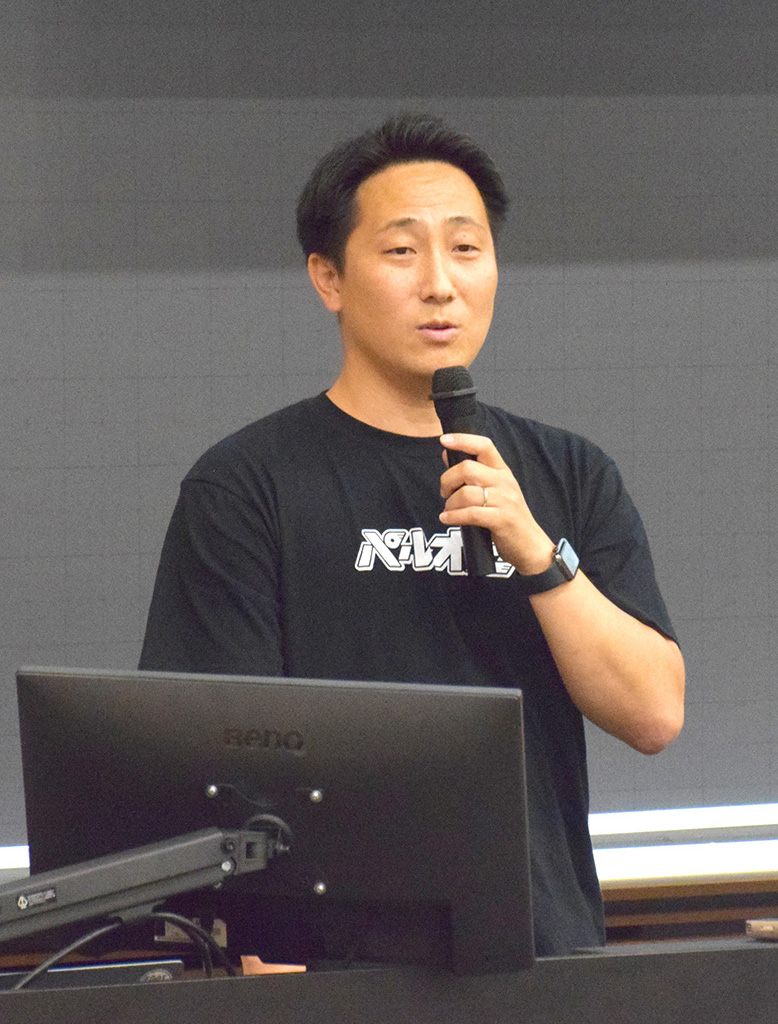
佐々木 惇氏
株式会社トリデンテ 代表取締役
元プロサッカー選手であり、マーケッターであり、起業家の佐々木さんの会社の企業理念は「社会課題にスポーツで答えを出す」。フィジカル事業で日本のトップスリーに入る企業に「トリデンテ」を成長させた佐々木さんの、元アスリートならではのビジネスでの成功の秘訣を伺える貴重な機会となりました。 「とりあえず、迷ったらやる」、「やると決めたら全力でやる」、「覚悟と決意が情熱になり、引力となり、その引力が、大きくなればなるほど、大きなことを成し遂げる事が出来る」など、スポーツマーケティングにおける金言が次々と繰り出され、学生の皆さんにも刺さっていたように思います。「大切なのことは、人が人のために想い、人のために尽くす」と語る佐々木さんの哲学に触れ、とても意義や意味ある授業となりました。
第12回(2024/7/11)
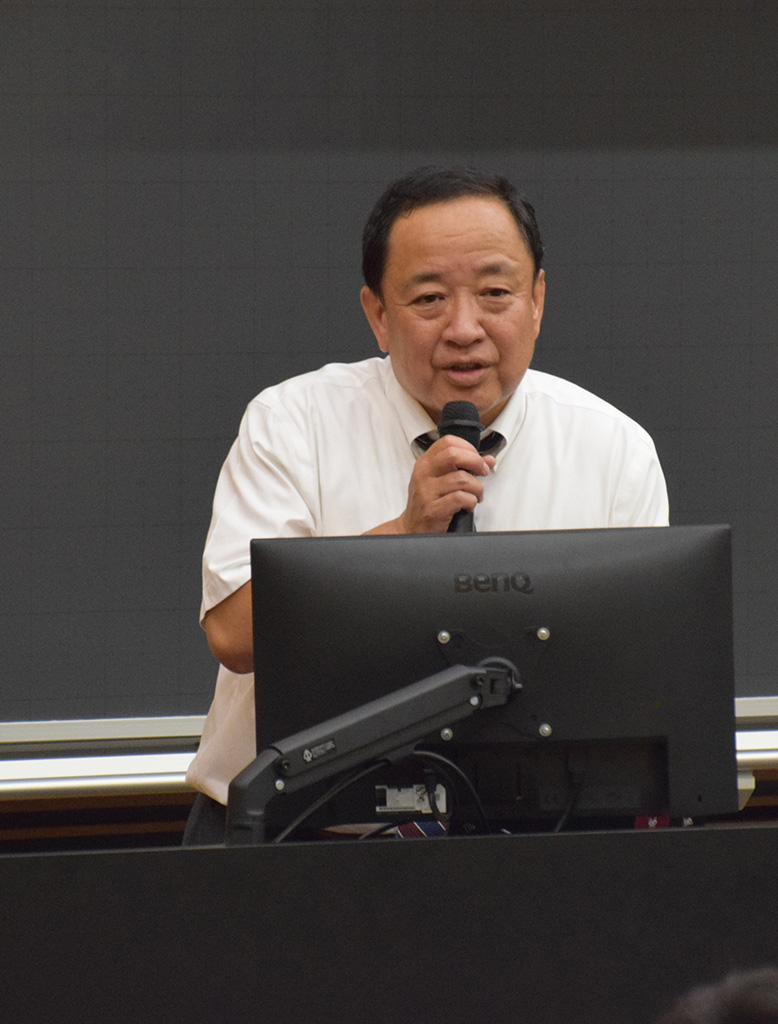
松井 一晃氏
株式会社文藝春秋 執行役員ナンバー局長
40年以上、スポーツの名場面、名選手を撮り続けてきたスポーツグラフィック「Number」の編集局長を迎え、アスリートが見せてきた人間の素晴らしさを、いかに伝えてきたのか、余すことなくご講義を頂きました。過去の雑誌の表紙の数々を軸に、時代に彩を与えてきた様々なアスリート達を紹介して頂き、その上で、スポーツの魅力を「人間の多面的な魅力が浮き彫りになる面白さがある」と語る松井さんの言葉に学生の皆さんは共感していました。 敗北を受け入れ、苦難を乗り越え、挑戦し続けられる人間力が大事だと続ける松井さんが、桐蔭横浜大学の学生に一番伝えたかったことは「言葉の持つ魅力を知り、自分の考えを自分の言葉で語る事の大事さ」でした。プロアスリートを目指す学生もいる中で、色々考えさせられる授業となりました。
第13回(2024/7/18)

今 淳一氏
株式会社ティップネス コンテンツ開発部
「アスリート・クロス」最後の講義として、これまでの総括が客員教授の岡部さんからありました。様々なスポーツビジネスの分野で活躍している特別講師の方々が、桐蔭横浜大学の学生たちに伝えたかった事は何か?全ての講義で共通している事は「人間力の大切さ」、「スポーツの持つ力の大きさ」、目標達成に向け取り組む「アスリートのポテンシャルの高さ」だと解説しました。「志と覚悟を持って、全力で継続的に頑張る事がビジネスの世界での成功要件」と語る岡部さんからは、「だからこそ、桐蔭横浜大学の学生の皆さんには、何でも出来る未来がある」という言葉が続きました。また、講義冒頭では、ティップネスコンテンツ開発部の今淳一さんからフィットネス事業におけるコンテンツ(プログラム)開発の紹介がありました。理学療法士でもある今さんの、人の身体に関する知識に裏付けされた話には説得力があり、「健康増進などに向け大事な運動継続には、いくつかの壁があるが、その壁をコンテンツの力や場の提供で乗り越え、カスタマーサクセスに繋げていく事が我々の仕事」という言葉を真剣に聞く学生たちの姿が印象的でした。


 instagramはこちら
instagramはこちら