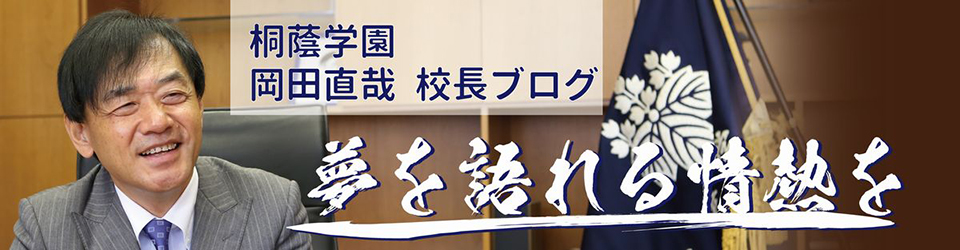桐蔭学園の学びの3本柱(アクティブラーニング型授業、探究、キャリア教育)の一つ、探究の授業のひとコマを紹介しましょう。
桐蔭学園では探究の授業を「未来への扉」(略して「みらとび」)とよんでいます。高校1年では、1学期に探究の基礎スキルを学び、2学期以降のゼミ活動へと進んでいく流れなのですが、今週あるクラスでは「身近なテーマを学問につなげてみよう!」というテーマで授業を展開していました。各自の進路選択に向けて目を開いていくことをねらいとしています。
「自ら決めた練習用の探究テーマを、自分が関心ある学問系統を中心に、各学問領域でどのような課題設定が可能であるか考えてみる」──高1にはなかなか難しいテーマですね。
しかし、いざ授業が始まると、各自が調べた内容についてペアワークで意見交換をしたり、大変積極的かつ楽しそうに取り組んでいました。
授業後の生徒のふり返り(一部)です。
「身近なテーマから大学の学部をたくさん知ることができたので、自分が選択したい学部のイメージが湧いてきました。自分に向いてそうなことや楽しそうだなと思ったことを、今後のためにしっかりと記憶しておきたいと思います」
「楽しかったー! 1つのテーマについて、いろいろな学問の視点から課題を見つけるのが楽しかった」
「今回の授業で自分はどんな分野の学問に興味があるのか、何を得意としているのかが少しずつわかってきて、自分の考えがはっきりとしてきたのが良かった」
「自分が1つだと捉えていた探究したいテーマは、実際細かく分けてみたことにより、身の回りの小さなことから、海外、世界の大きなことにまでつながっているのだと気づきました」
「人の心を表現したり、動かしたりするには? というテーマから、学問領域につなげて考えることができた。私一人ではなかなか思いつかなかったけれど、人と話し合うことで理学や工学の観点からも課題を考えることができ、意見交換の大切さを感じた」
──これらのコメントからも、生徒たちは大変前向きに、そして好奇心を持って取り組んでいることがわかります。生徒自らが疑問に思っていることと学問とが結びつき、そこから自分自身の進路について考え始めるきっかけになったのではないでしょうか。
「生徒たちはペアワーク、グループワークを通じて新たな気づきの大切さを理解し始めています。改めて生徒たちの逞しさを感じています」とは、授業担当者の言。
「学び」とは、新たな気づきを得ること。そして新たな気づきは「感動」を生みます。「ああ、そうだったのか!」という感動です。これこそが「学び」の意義であると信じています。